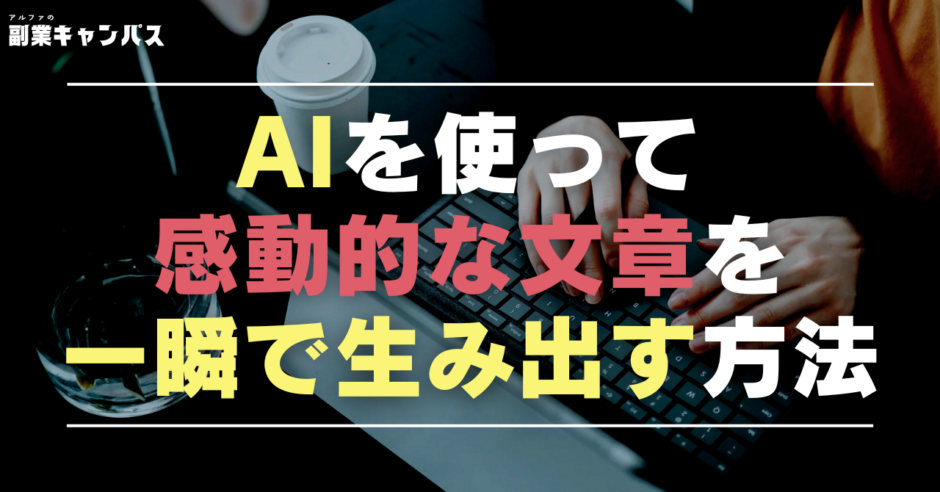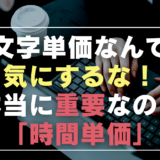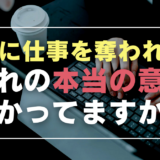AIの進化によって、誰でも「そこそこ読める文章」を簡単に生成できる時代になりました。
ChatGPTなどを使えば、テーマさえ指定すれば数秒で体裁の整った文章が出てきます。
ですが、そんな“便利な時代”だからこそ、求められるのは「心を動かす文章」。
読み手の感情に訴えかけ、共感や感動を呼び起こす文章は、AI任せでは生まれません。
僕自身ライターとしてもディレクターとしても、YouTubeの台本や記事制作に関わる中で、
「AIに任せきりでは通用しない」という現実を痛感しました。
そこでこの記事では、
感情を揺さぶる文章をAIに書かせるための具体的な方法を、
実体験を交えて解説していきます。
AIはまだ使えないと思い込んでいた理由
僕が初めてAIを仕事で使ったのは、今から1〜2年前のことです。
とあるYouTubeチャンネルの台本を担当していたとき、クライアントから
「次回からAIを使って書いてほしい」と言われ、GPTsを渡されました。
「こんな便利なものがあるなら使ってみよう」と軽い気持ちで取り組んだのですが、結果は散々でした。
AIが出力する文章は、いかにも「とりあえず情報を並べただけ」といった感じで、
読み手の心を動かすどころか、テンプレ的で薄っぺらい。
クライアントにも正直に「試してみましたが、これでは通用しません」と伝えることになりました。
このとき僕は、「やっぱりAIに文章は無理だな」と強く思ったんです。
クライアントが指定してきたGPTsの完成度が低かったのかもしれないのですが、
「これなら自分で書いた方がいい」と判断し、その仕事ではAIの使用を断念しました。
この経験もあり当時の僕にとって、AIは“まだ実用に耐えない未完成の道具”という認識でした。
ですが、仕事仲間に誘われて参加したAI合宿で、僕は衝撃を受けることになるのです。
AI文章のクオリティが劇変した“設計力”の正体
AIなんてまだまだ使えない——そう思っていた僕の考えが大きく変わったのは、「AI合宿」に参加したのがきっかけでした。
YouTubeチャンネルのオーナーに「AIを使って台本を作るノウハウが学べる合宿があるんですけど、どうですか?」と誘われたんです。
正直、最初はそこまで期待していませんでした。
あの失敗経験もあったので、「また大して変わらないんじゃないか」と思っていたんですが…。
実際に参加してみて、僕の中の“AIに対する認識”は一変しました。
そこで教えてもらったのが、「プロンプト設計の重要性」でした。
ただ「◯◯について書いて」と指示するのではなく、読者像、トーン、構成、エピソードの入れ方など、前提条件を細かく指定する方法を学んだのです。
それまで僕は、AIを“使う”ことばかり意識していました。
でも、本当に大切なのは「どう設計するか」だったんです。
プロンプトを丁寧に組み立てた上で出力された文章は、それまでのものとは全くの別物でした。
情報が整理されていて、言葉に力がある。
そして何より、「読者の心を動かす力」があったんです。
「AIって、ここまでやれるのか…!」
そう感じた瞬間から、僕のAIへの向き合い方が大きく変わりました。
今では、プロンプト設計は“AIに魂を入れる作業”だと思っています。
ただ便利なツールとして扱うのではなく、設計という視点を持つことで、AIは圧倒的なパートナーになる。
それを教えてくれたのが、あの合宿だったんです。
誰でもできる!感動的な文章をAIに書かせる5ステップ
AIに感動的な文章を書かせるには、“ただ指示を出す”のではなく、“感情が動く仕組み”を理解させる必要があります。
そのための方法が、以下の5ステップです。
初心者でもすぐに実践できるので、ぜひ試してみてください。
ステップ①:感動的だと思う台本・記事を3本選ぶ
まずは「これはいい!」と感じた文章を3本ピックアップします。
ジャンルはYouTube台本でもブログ記事でもOK。
ここで大事なのは、自分が“感情を動かされた”と実感した文章を選ぶことです。
ステップ②:ChatGPTに「なぜ感動するのか?」を分析させる
選んだ文章をChatGPTに貼り付けて、こう聞いてみましょう。
「この文章が読者の感情を動かしている理由を分析して」
1本だけだと偏るので、3本を同じチャット内で連続して分析させるのがポイントです。
ステップ③:分析結果をもとに「前提条件」を洗い出す
ChatGPTが提示してくれた要素から、
「共感できる語り口」「具体的なエピソード」「読者視点の問いかけ」
などの要素を抽出します。
この工程が、AIに“感動の型”を教えるプロセスになります。
ステップ④:GPTsの指示欄に追加で貼り付けてテスト生成
洗い出した前提条件を、GPTsの「指示文(プロンプト)」欄に貼り付けます。
これで毎回プロンプトを打ち直す必要がなくなり、再現性の高い出力ができるようになります。
ステップ⑤:出力をレビューして、指示文を改善
実際に文章を生成させてみて、「なんか違うな」「ここは良いな」と感じた点を元に、プロンプトを修正・追加します。
いきなり完璧なプロンプトは作れません。
試して→修正して→また試す。
この繰り返しが、AIの出力精度を進化させてくれます。
このステップに沿って進めるだけで、AIはただの情報整理マシンではなく、“感情を動かすクリエイター”へと変わっていきます。
しかもこの作業、やってみるとけっこう楽しいんです笑。
ちょっとした言い回しの工夫で、グッと伝わる文章に変わるのがたまらないんですよね。
ぜひ、自分の“感性”をAIに教え込む感覚で、プロンプト設計に挑戦してみてください。
実際に僕が使っているGPTsテンプレート
GPTsの設計方法をお伝えしましたが、正直いきなり実践するのは難しいと思います。
そこで、今回は特別に僕が使っているテンプレートを一部ご紹介します!
以下がm僕が実際に使っているGPTsテンプレートの設計要素です。
1. 想定読者
誰に向けて書くのか?
・初心者なのか、経験者なのか
・どんな悩みを持っているのか
これを明確にすることで、言葉選びや語り口が変わります。
ちなみに、この想定読者もAIに質問すればすぐに洗い出してくれますよ。
2. 記事構成
導入、問題提起、具体例、アクションプラン、まとめ──など、
文章全体の設計図を事前に組んでおくと、AIも迷わずに内容を整理できます。
もちろんこれも、AIに競合の記事を複数分析させるなどすれば、
最適な構成を考えだしてくれます!
3. 必ず入れるエピソード要素
自分自身の体験、失敗談、学びなど。
読者の感情を動かすために必要な要素を指定しておきます。
これはジャンルによって入れるべき要素が変わってくるので、あなたのジャンルに合った内容を指定しましょう。
エピソードだけでなく、科学的な根拠や社会的な証明を入れて、という指示も適切ですね。
エピソードや経験談を入れて欲しいときは、
「どんな場面で、何を感じ、どう変わったか」といった感情の流れを具体的に指定しておくと、
読者の共感を得やすくなります。
4. トーンと文体の指示
・フレンドリーかつ丁寧
・論理的でありながら人間味のある表現
・読者を励ます口調
こういったニュアンスも、プロンプトにしっかり記述しましょう。
5. 競合の文章の分析結果
自分が目標とする「感動的な文章」の特徴を、分析結果として盛り込んでおくことで、
AIの出力が“理想に近づく精度”で整います。
これを入れていない人が多いのですが、精度がガラッと変わる大切な要素なので
必ず入れるようにしてください。
このテンプレートをベースに、自分の文体や目的に合わせて微調整していくことで、感情を動かす文章を作ってくれる、
あなただけのAIが完成します!
また、僕自身はプロット用と本文用でGPTsを分けて運用しています。
たとえば──
- プロットGPT:構成やテーマを整理する
- 本文GPT:構成に沿って一気に書き上げる
このように「0→1」と「1→10」の工程を分けることで、AIの出力精度は格段に上がります。
一つのGPTに全部を任せようとすると、AIも混乱してしまいます。
役割分担することで、AIが「今、何に集中すべきか」を明確にできるため、出力の精度が上がるのだと思います。
AIは使い方次第で「木の棒」にも「核兵器」にもなる
AIがここまで進化した今、どう使うかが、ライターとしての価値を大きく左右する時代になりました。
ちょっとした文章を生成するだけなら、誰でもできます。
でも、それだけでは埋もれてしまいます。
これから求められるのは、「AIに何をさせるか」を設計し、自分の表現力と掛け合わせる力です。
少しハードルが高いと感じるかもしれませんが、GPTsの使用にぜひ挑戦してみてください!
ここまで読んでいただきありがとうございました!
「副業を始めたい!」「副業をしているけどうまくいかない…」
そんなあなたは以下の黒いボタンから「メルマガ」に登録してください!
僕が現場で体験してきた知見や、ゴリゴリ稼いでいるフリーランスから聞いた話などを配信しています!
↓↓↓